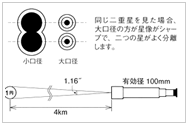天体望遠鏡の基礎知識 | 取り扱いブランド
天体望遠鏡の基礎知識
天体望遠鏡の基礎知識
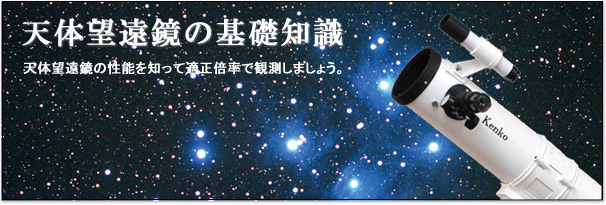

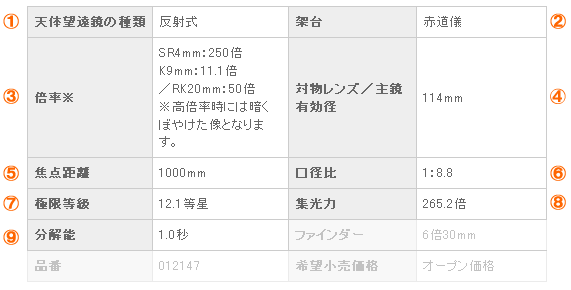
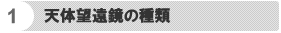
- 屈折式
- レンズを使って光を集め像を作る天体望遠鏡です。 対物レンズには、像の色のにじみを少なくするために、異なる性質の2種類のガラスを組み合せたアクロマートレンズ(色消しレンズ)が使われています。
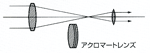
- 反射式
- 光を集めて像を作るために、ガラスの表面をメッキした反射鏡(凹面鏡)を使用した天体望遠鏡です。 反射望遠鏡にはニュートン式、カセグレン式などいろいろな種類があります。 ニュートン式は凹面鏡(主鏡)からの光を光軸に対し45°の角度に置いた平面鏡(斜鏡)で90°曲げて像を作り、これを接眼部レンズで観察するもので、有名なニュートンにより発明されたのでこの名があります。
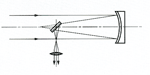
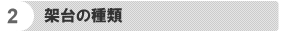
望遠鏡を支える架台には経緯台と赤道儀式の2タイプがあります。観測目的に応じて選びましょう。
- 経緯台式
- 経緯台式では星の動きに対して左右、上下の2方向へ望遠鏡を動かすことができます。 操作が簡単ですので、はじめて天体望遠鏡をご使用になる方をはじめ、学習用としても最適です。
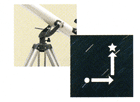
- 赤道儀式
- 赤道儀式では星の動きに対して赤経ハンドルひとつの操作で星を捉えつづけることができます。 長時間の観測、写真撮影に最適ですが、使用前に極軸のセッティングが必要です。 また、モータードライブの使用による完全自動化が行え(取付可能機種に限る)、初心者から上級までレベルに応じたシステムアップが可能です。
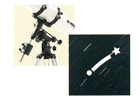


望遠鏡の倍率は対物レンズ/主鏡の焦点距離を接眼レンズの焦点距離で割ることで求められます。 例えば、焦点距離900mmの望遠鏡で20mmの接眼レンズを使用した場合、900÷20=45(倍)となります。
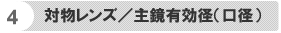
対物レンズや主鏡の実際に使われている部分の大きさを直径で表したものです。 有効径が大きいほど光をたくさん集めることができ、明るい視野を得ることが可能です。 星雲や星団などの暗い天体を観測する際はなるべく有効径の大きい望遠鏡をおすすめします。
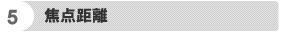
対物レンズの中心または主鏡の中心から像を結ぶ焦点までの長さを焦点距離と言います。
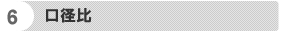
焦点距離を対物を対物レンズ/主鏡有効径で割ったもので、1:15のように表されます。 数値が小さくなるほどの明るいレンズであることを表します。
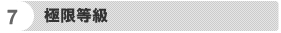
どれくらい暗い星まで見えるかを表したものを極限等級といいます。 肉眼での極限等級は6.5等星くらいまで(光害は考えない)で、望遠鏡では対物レンズ/主鏡有効径が大きくなるほど暗い星まで見ることができます。
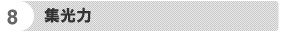
肉眼に比べて何倍の光を集めることができるかを示したものです。 対物レンズ/主鏡有効径が大きくなるほど暗い星まで見えるようになります。
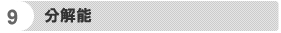
二つの接近したものを見分ける能力です。 分解能は1.16"÷対物レンズ/主鏡有効径(mm)の式で求められます。 例えば対物レンズ/主鏡有効径が100mmのときはこの式より分解能は1.16"となりますが、これは4km先にある1円玉の大きさに相当しますから、非常に細かいものを見分けられることがわかります。

望遠鏡は倍率が高いほど良く見えると思われがちですが、そうではありません。 口径が同じであれば、ある程度以上に倍率を高くしても、像は暗くなり、ボケて見えにくくなるだけで、細かいところまで良く見えるようになりません。 この限度を最高倍率といい、口径をmmで表した数の2倍くらいが目安となっております。 例えば、口径60mmなら120倍、口径100mなら200倍が最高倍率となります。 一般の観測では口径をmmで表した数からその半分くらいの倍率が最も観測に適した倍率(適正倍率)になります
- 口径60mmの場合
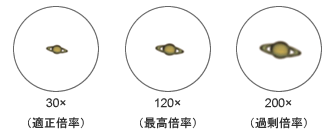
- 口径60mmから100mmまでの望遠鏡でどの程度見えるか
-
天体 倍率 見える程度 月 40×~150× 無数のクレーターや山脈、海の凹凸 水星 60×~100× 三日月形がわかる 金星 60×~100× 満ち欠けや大きさの変化がわかる 火星 90×~150× 大接近の時、うすい模様が見える 木星 70×~150× ガリレオ衛星、しま模様が見える 土星 70×~150× 環や本体のしま模様が見える 二重星 40×~150× 100個以上見える 変光星 30×~50× 10等級以上のもの約500個 星雲・星団 20×~100× 200個以上見える