第3回 星景写真を極めるための周辺機器について
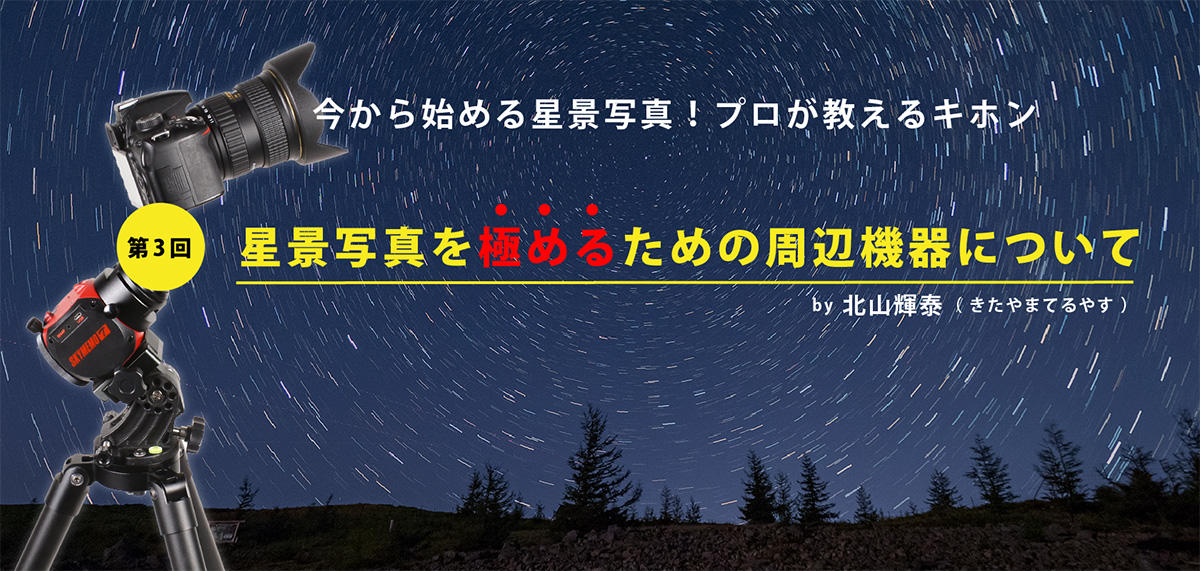
第1回目はこちらをご参照ください。
第2回目はこちらをご参照ください。
もう一歩星景写真の世界へ踏み出そう
第1回、第2回と星景写真について触れてきた本特集記事もいよいよ第3回目となりました。
これまでは、基本的な星景写真撮影に必要な機材や、撮影方法についてご紹介してきましたが、第三回目では、 星景写真をより楽しむための周辺機器 赤道儀 について触れていきたいと思います。
赤道儀(せきどうぎ)を使った星景写真の世界
みなさんは、赤道儀という機材をご存知でしょうか?
赤道儀とは、簡単に言うと星の日周運動(東から昇って⻄へ沈んでいく動き)と全く同じ速度で回転する機構を持った機材のことを言います。
1時間に15度といってもあまり実感がわかないかもしれませんが、ずっと夜空を見続けていないとわからないくらいのゆっくりとした速度で動くのが特徴です。
では、この赤道儀があると何ができるのか。それは「星を追いかけながら撮影をする」ことができます。 しっかりセッティングしさえすれば、30 秒以上、例えば1 分や2 分間シャッターを開けていても星を点像で撮影することができます。
■30 秒間シャッターを開けて撮影をした写真。
拡大してみるとはっきり動いているのがわかります。(画像をクリックすると拡大します。)
■赤道儀を使用して、まったく同じ設定で撮影をした写真。
星の動きを追いかけながら撮影をしているため、点像になっています。
赤道儀を使用するメリット
星を点像で撮影することができる赤道儀のメリット。
それは、標準〜中望遠レンズを使用した迫⼒のある星景写真に挑戦できること だと言えます。
いくつか作例をお見せします。
同じ場所で、広角レンズと標準レンズ、二つのレンズで撮り分けて見ました。「八ヶ岳から登る夏の天の川」というテーマの作品を撮りたかったため、⻑野県霧ケ峰より撮影を⾏いました。
14mm(35mm 判換算)で撮影した写真は、天の川を大きく撮ることができていますが、八ヶ岳の稜線(画面左側)が小さく写ってしまっています。これでは肝心テーマが薄れてしまいます。そのため、ここでは焦点距離を⻑くして撮影する必要が出てきます。
28mm(35mm 判換算)で撮影を⾏いました。八ヶ岳の稜線をクローズアップして撮ることができています。この時、赤道儀を使って撮影を⾏っているので、夏の天の川もしっかりと存在感を残しつつ撮影を⾏うことができました。
こういった焦点距離を⻑くして撮影をしたい時に、赤道儀が活躍します。ご覧いただければお分かりになりますが、1分程度までの露光時間であれば、地上風景のブレはそこまで目立ちません。
赤道儀を使うことで、星座の写真撮影に挑戦することもできます。星座の撮影は基本的に24mm〜50mm程度(35mm 判換算)の焦点距離のレンズを用いることが多いですが、これらの焦点距離ではどうしても星が流れてしまうのが目立ってしまうため、赤道儀は必須になります。さそり座のアンタレス付近や、オリオン座付近のバーナードループは、赤道儀を使ってぜひ撮影したいもらいたい被写体です。
さらにもう一つ赤道儀を使うメリットとしては、F値を絞って撮影をした時でも綺麗な星景写真が撮れるということです。 F値を絞って撮影をするメリットとしては、絞り開放で撮影をした時特有の
- 周辺減光
- コマ収差
- サジタルコマフレア
の発生を最小限に抑えることができることが挙げられます。
左の写真は、中心部分が明るく四隅にいくにつれて暗くなっていくのに対し、右の写真は明るさがフラットになっているのがお分かりになるかと思います。レンズの設計上、どうしても発生してしまうこれです。
話は少しそれますが、F値が明るいレンズは、確かに星空写真の撮影に非常に有利ですが、大口径のものが多く重量もあり、さらに値段も比較的に高めとなっています。そのため、なかなか手が出しづらいという方も多いのではないでしょうか。
安価なレンズは、F値が暗く星空写真の撮影に不向きだと思われがちですが、赤道儀があれば、⻑時間露光をしても綺麗な星空写真を撮ることができます。高価なレンズを買う代わりに赤道儀を購入するという別の選択肢があることもぜひ覚えておいていただければと思います。
赤道儀の種類
赤道儀は大きく分けて「天体望遠鏡用の大型のもの」と「カメラ用の小型のもの」の2種類があります。 天体望遠鏡用のものは、高価でセッティング方法などの異なるため、今回はカメラ用のものをいくつかご紹介します。
形は様々ですが、これらはみんな同じ用途として使うことができる赤道儀です。赤道儀はカメラ三脚の上に取り付けて、その赤道儀に自由雲台を取り付けた上、最終的にカメラを載せるという組み立て方法になります。
さらに、より重い機材に耐えられるよう、スカイメモTとSには、専用の三脚と微動装置が別売りで販売されています。
ASTRA ECH-630 もスクエア型のユニークな形をしていますが、こちらも赤道儀です。
ECH-630 の魅⼒は、何と言ってもその連続駆動時間です。単三電池4 本でおおよそ20時間(20°の環境で)の駆動ができるため、⻑時間星空を追いかけながら撮影したい時に重宝します。さらに、多彩な速度変化の機能が搭載されているため、タイムラプス撮影用としてもオススメです。
赤道儀のセッティング方法
これらの小型の赤道儀には、素通しの穴(ポーラファインダー)と呼ばれるものが付属されています。この穴を片目で覗きながら、穴の中に北極星が来るように赤道儀が乗っている自由雲台を操作する(=北極星の導入)というのが最も一般的な方法です。これを天文用語で、極軸合わせと言います。
また、極軸望遠鏡が付属しているタイプの赤道儀は、それを使ってより厳密に北極星を導入することもできます。こうすることで、より焦点距離が⻑いレンズを使って撮影する時にでも、⻑時間星空を追いかけることができます。
北極星を導入する作業は非常に難しいのでは?と思われる方が多いかもしれません。確かに最初は正確に北極星を導入するのがうまくいかないことも多々あるかと思います。ですが、星景写真撮影では、基本的に広角レンズを使って撮影をしますので、そこまで厳密に合わせる必要はありません。なんとなく北極星の方角に向いているかな?という具合でも、30 秒程度であれば特に問題なく追尾できるかと思います。まずは赤道儀のセッティングに慣れて、そこから徐々に極軸合わせの精度をあげていくぐらいの簡単な気持ちで使い始めていただければと思います。
まとめ
今回は、星景写真の周辺機器として、赤道儀をご紹介しました。赤道儀を用いることで、星景写真の世界はグッと広がります。さらに、赤道儀のパーツを買い揃えていけば、カメラ用の望遠レンズをのせて簡単な天体写真撮影に挑戦することもできるようになりますので、ぜひこの機会にチェックして見てください。
さて、次回はいよいよ最終回ということで、星景写真撮影をより楽しむための星空の知識についてご紹介したいと思います。
今から始める星景写真!プロが教えるキホン 記事一覧

北山輝泰
皆様、初めまして。この度、星景写真についての記事を執筆させていただくことになりました、写真家の北山輝泰( きたやまてるやす )と申します。
専門は星空の写真です。星景写真や星座写真を中心に、国内はもちろん、年に数回、海外に行って撮影もしています。写真を撮ることも好きですが、星空の神話や星の名前の由来などを調べたり、プラネタリウムや科学館を巡るのも好きです。
また、NIGHT PHOTO TOURSという団体を立ち上げ、夜をテーマにしたワークショップを企画し、運営しております。ご興味がございましたらぜひお問い合わせいただければと思います。

