初めての星景写真「#1 星を撮ろう」
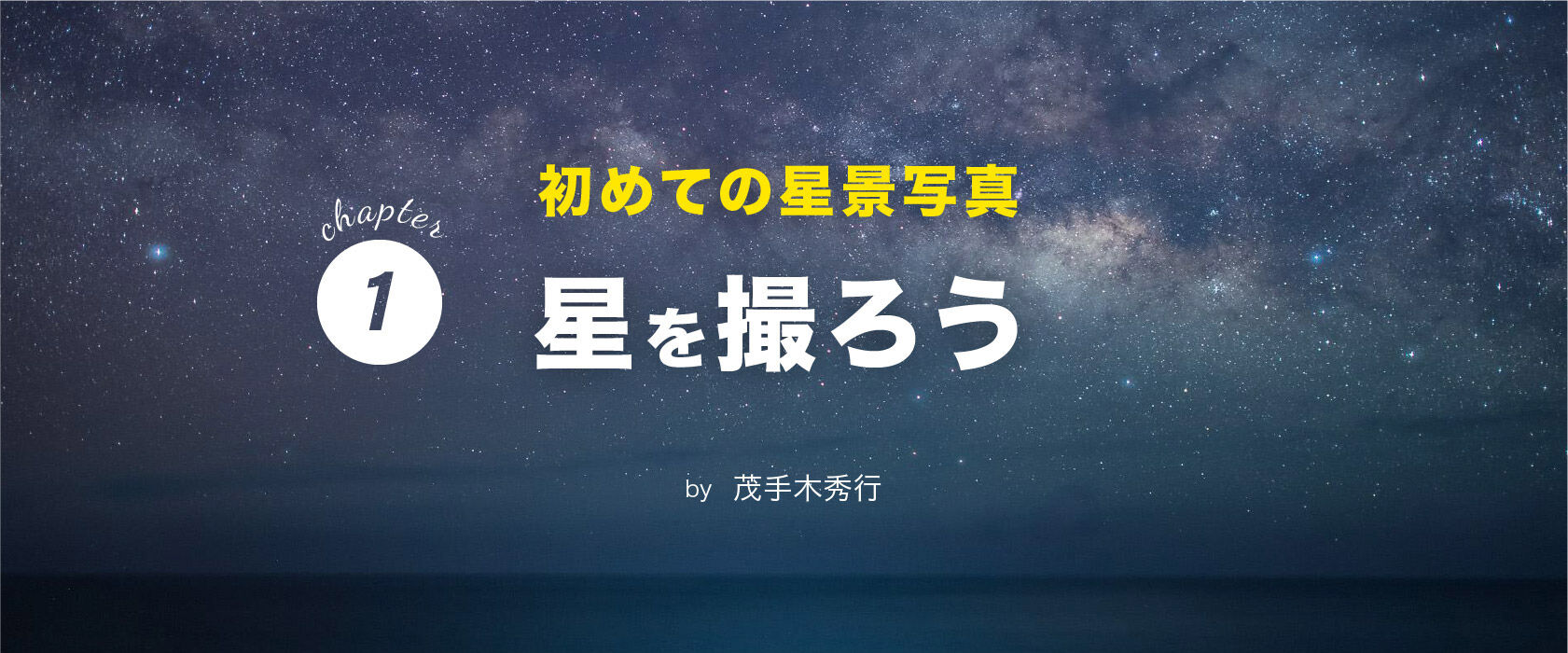

写真家 茂手木秀行(もてぎ ひでゆき)
1962 年東京生まれ。日本大学芸術学部卒業後、出版社マガジンハウス入社。2010年フリーランスとなる。1990年頃よりデジタル作品制作と商用利用を始める。中学生の時に天文部に所属して以来、天体、星景の撮影はライフワークであり、多くの個展やセミナーを行ってきた。JPS 正会員、APA 正会員、写真学会会員
初めての星景写真
デジタルカメラの高性能化により、近年急激に星空の撮影を楽しむユーザーが増えてきた。 しかしながら、通常の撮影とは勝手が違うことも多く、最初の一歩が踏み出せないユーザーの声を 多く聞くようにもなった。本稿はそうしたユーザーの手助けとなるよう心がけ記してゆく。とはいえ 本項だけではわからないことも多いかもしれない。わからないことは他の資料にも当たり、一つ一つ知って いこう。知ることの喜びも写真の大切な要素であるからだ。
ともあれ、星空の下静かな空気に包まれる時間を楽しんでほしい。表紙の写真は春の夜明け、東の空から横 倒しに登ってくる天の川中心部だ。毎年この時期を楽しみにしている。宇宙の中にいることを実感しつつ、 夜明けを待つ。その静かな時間が豊かで、大切なものであると心底思えてくるのだ。
星景写真とは
「星景」とは星空風景の略である。近年ユーザーが増えることですっかりその名称は定着したものと思う。 天体写真と風景写真の要素を兼ね備えた写真という定義になるが、天体写真から見ると同じように星空を 撮っても違う分類となる。簡単なことであるが、地上の風景を含むと星景写真、地上の風景を含まなければ 星野写真と呼ばれる。
なぜそのような分類をするかといえば、星野写真では当然ながら風景写真の要素を含まないため、被写体と して着目すべきは星座、アステリズム(目立つ星の並びを結んだもの)、星雲や星団などとなりそれらの特 徴や性状を捉えつつ、矩形の画面の中にバランスよく配置することが構図決定の要となる。一方、星景写真 では同じように星座、アステリズム、星雲・星団に着目するもののそれらを画面に取り込まれた地上風景の 一部とみなし、画面あるいは構図を構成する一要素として扱う。また星野写真における主題は必ず特定の天 体(前述の被写体全て)であることに対して、星景写真では主題と副題は等価であり、星空が必ず主題となる必要はない。
星を点に写すか、光跡として写すか
星景写真の技法は単に長時間露光であり、夜景撮影などと変わりはない。夜景撮影で車のヘッドライトが光跡として写るように星景写真でも星が光跡として写る。露光時間を短くすれば星は点として写るが、露光時間を長くすれば星は光跡として写る。星は地球の自転により見かけ上動いてゆくが、それを日周運動という。日周運動の結果光跡を引くのである。点として写せばひとつの時間の記録として捉えることができ、写真としてのリアル感を持つことができる。一方、光跡として写すと人間の目には知覚できない現象の結果として写り、時間や自然の雄大さを表すモチーフとなる。
星景写真撮影に最低限必要なもの
前述の通り、星景写真の技法は長時間露光である。始めるにあたっては、特別な機材を必要としない。必須
のものは三脚とレリーズのみだ。もし、持っていないならこの機会に手に入れてはどうだろう。星景写真以
外でも必要になる機材である。
星景写真に限っていうならば三脚は軽い分、大きさを稼げるカーボン製が良い。大きく開くことで安定性を
確保しつつ、軽くて移動が楽だからだ。

おすすめ三脚はSlIK カーボンマスター 823 PRO N
雲台は自由雲台が星景写真に向いている。

レリーズも大きい方が良い。冬には手袋をしたまま操作することが多いからだ。リモート90L 各社用(ニコン、キヤノンなどは複数のコネクターがあるのでよく適合を確認のこと)
星座を学ぶ
どのような分野の写真も、被写体をよく知り観察することが第一である。 星景写真は天文学への興味の扉でもあると言えるが現代の天文学全てを知ることは不可能だ。
最初の一歩は星座を知ることから始めよう。現在の星座は1922年に国際天文学連合(IAU)によって提唱され、全天で88の星座がある。 日本の有人地域からは星座の一部を含めると83個の星座を見ることができる。88の星座全てが星景写真の主題となることはないが、星座は人間の時間尺度においては普遍のものであり、写っている星座からおよその撮影場所、日時を知ることができる。それゆえ、星景写真においては季節を表すモチーフであり、その並びとともに重要な被写体なのだ。少なくとも四季に対応する星座は知っておきたい。
星景写真の被写体にしやすい星座
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
星座アプリ
ここでは星座を学ぶこと、撮影の計画を立てることに役立つアプリケーションを2つ紹介する。
Stellarium
Stellarium は無償で提供されるパソコン用プラネタリウムソフトウェア。Linux、Windows、macOS 版がサポートされている。場所と日時を設定するとその時の星空を表示でき、星座の形や結び方、星雲・星団・彗星などの天体に関する情報も学ぶことができる。ビジュアルも美しく日本語化もされているので、インストールしておいて損のないソフトウェア。
Skysafari
星景撮影の現場に最もおすすめのソフトウェアはSkysafariである。パソコン用はMac OSのみであるが、スマホ・タブレット向けではiOS版、Android 版がサポートされているので、撮影現場むきといえよう。製品はいくつかのバージョンに分かれており、iOS 版のみバージョン7、その他はバージョン6である。バージョン6の中でもスタンダード・Plus・Proと分かれている。バージョン7ではPlus・Pro の2種である。いずれのバージョンでもおすすめはPlus だ。Plus とPro の違いはほぼデータベースの違いのみで、Proはその名の通り職業的天文学者向けのアプリなのである。スマホ・タブレット用のPlusであれば、スマホの向きに合わせて星座を表示する機能とAR機能がある。また、Mac 版も含めて望遠鏡コントロール機能、撮影画角表示機能を備えており、星景撮影、天体撮影全般に欠かせないアプリとなっている。英語版のみ。
Stella Navigator
WindowsユーザーへのおすすめはStella Navigatorである。日本製のソフトウェアであり使いやすく多機能である。歴史の古いソフトウェアで日本の天文ファンのデファクトスタンダードとなっている。望遠鏡コントロール、撮影画角表示、撮影結果のシミュレーション、天文計算など星景・天体撮影に必要な機能を最も幅広く網羅している。深く天体撮影にのめり込みたいユーザーにお勧めだ。
撮影シミュレーション
前述のSkysafariを使うと詳細に撮影計画を立てることができるので活用しよう。
ここではiPad版Skysafari7Plusを例に基本的な手順を追うが、その他のソフトウェアでも概ね同じような
流れとなるので参考として貰いたい。
手順の大まかな流れはレンズの登録 → カメラの登録 → 表示の設定である。画角を表示してシミュレーション すると撮りたい星座をいつ撮影するとバランスよく風景を取り込めるかがわかるのだ。
- 1Skysafariを起動したら下部にあるSettingsをタップ
-

- 2サブウインドウからGrid&Referenceをタップ、Show Grid・with Horizon Coordinatesを選ぶ。
-
*note:左側の項目上方に日時、場所の設定があるのでここで設定しておくと良い。

- 3高度と水平の座標線が表示される。
-

- 4下部Observeをタップ、MyEquipmentを選ぶ
-

- 5サブウインドウが開くので、ここでTelescope(レンズ)とCameras を設定する。 Telescope をタップ、表示されたCreate Custom をタップする。
-


- 6Create Custumボタンをタップし、まずレンズの情報を登録する。ここではSmyang AF24mm F1.8 FEを例にした。Aperture はレンズの有効口径であるが、画角表示に限れば重要ではないので適当な数字でも構わない。重要なのはFocal length(焦点距離)である。設定したら下部に表示されるAdd To My Equipmentをタップする。Doneではないので注意。
-


- 7引き続いてカメラの設定をする。重要なポイントはセンサーのピクセル数と1画素のサイズである。メーカーHP で画素数とセンサーサイズを確認し、1画素の大きさを求めてから入力する。ここではSony α7S Ⅲとした。
-

- 8My Equipmentでの設定が終わったら、ObserveからScope Displayを選ぶ。
-

- 9Create FOVをタップ
-

- 10サブウインドウからFrom Equipmentを選ぶ
-

- 11Telescopes、Cameras をそれぞれ選び、先ほど入力したレンズとカメラを選ぶ。2つが設定されると下部にあるFOV インジケーターが赤からグリーンに変わる。
-

- 12左上矢印をタップして一つ前(Scope Display)に戻るとレンズとカメラの組み合わせが表示されているので○をスライドさせてアクティブにする。しかし、まだこの段階では画角は表示されない。 上部Done左隣の設定アイコンをタップする。
-

- 13サブウインドウが開くので、3つのボックスにチェックを入れる。Cardinal Directions は方位の表示、Draw Labels はレンズとカメラの名前を表示。最後にShow Even if Not Connected to Telescope だが、本来この機能は外部コントロールに対応した天体望遠鏡を接続した時に表示される機能である。よって未接続時も表示をチェックしないとならないのだ。
-

- 14以上でアプリ画面に、高度・方位のグリッドと撮影視野角が表示された。次に画面左上の時刻表示をタップする。
-

- 15すると下部に時刻バーが表示される。早送りボタンをタップすると左のボックスの設定で連続的に時刻送りがされる。カレンダーアイコンからは直接日時を指定することもできる。本画面での設定 は2022 年3 月2 日午前2 時49 分である。以上の設定によって、この時刻に24mm レンズを東北東、 高度15 度付近に向けて設置すると月明や薄明の影響なく、横倒しに登ってくる天の川の中に浮か ぶ夏の大三角と地上の風景をバランスよくフレーミングができることがわかる。
-

撮影の手順
まさに今日初めてというユーザーでも参考になるように撮影の手順を表にまとめた。大項目1〜5が順番、 小項目a~eが要素だ。小項目は順番が前後しても構わない。一旦仮に構図を決めてから、ピント合わせのた めあえて構図を崩して明るい星を視野中心におき、ピント合わせののちに再度構図を合わせ直すというのが 大きな流れとなっている。
| 手順 | 場所 | 目的 | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明るい場所で | カメラの設定 | リモートケーブルやスマホアプリを準備 | マニュアルフォーカス手ぶれ補オフ | 露出モード:マニュアル ホワイトバランス:オートもしくは4000K |
絞りF2.8 露光時間5秒 ISO3200 に設定 |
|
| 2 | 星空の下 | 仮に構図を決める | 三脚に乗せて一度構図を決める | ||||
| 3 | ピント合わせ | 絞りを開放に | ズームの場合は望遠側に | 1等星か2等星を視野の中心に | ライブビューに切り替え | ライブビューを最大に拡大 | |
| 4 | 再度構図を決め直す | 絞りを設定し直す | ズームの場合は構図を決めた時の焦点距離に | ||||
| 5 | 水平の確認 | ライブビューに切り替え | 水準器を表示 | 構図が変わらないように注意しながら水平に |
表の中の注意点をいくつか記しておくので参照にされたい。
1-c 近年のカメラであればWBオートがおすすめ。試写して好みでなければWBをマニュアルにして4000Kから前後して試すと良い
1-d 開放絞り値がF4などのレンズでは絞りF4露光時間8秒ISO4000とする。またこの露出値はテストのためのものであり、この値で適正露出になるわけではない。
2-a 仮の構図なので水平などは気にしなくて良い。ミラーレスではライブビューや電子ファインダーで星が見 えにくい場合がある。その場合は数枚試写を行なって、概ねの構図を決める。ズームレンズではここでズームの 焦点距離を決めるので、ズームリングの表記などで焦点距離を確認しておく。
3-a、3-b 絞りを開放に設定し直してから、明るい星を視野中心におく。この時点で仮の構図は崩れる。
5-a 夜間は目視ではカメラの水平がわかりにくいため、ライブビューの水準器を使う。傾けて動きを出すなど 水平を取らない場合はこの項目は不要。
レンズについての一般論
レンズは絞り開放で使うよりも、絞ることで段々とシャープさが増してくる。多くのレンズで絞りF5.6 からF8 で全画面で最良のシャープさが得られる。しかし、星景写真では少しでも露光時間を短く、あるいはISO 感度を 下げたいため少しでも絞りを開けて撮影したい。一般に大口径単焦点と言われるF2 よりも明るいレンズでは F2.8 程度に絞ると画面の大半でF5.6 やF8 に絞った時と遜色のないシャープな像が得られるものがほとんどで あるため、単焦点レンズではF2.8 を基準とすると良い。またズームレンズでも開放F2.8 の系列は各メーカー の顔ともなるべき高性能レンズを揃えているので、やはりF2.8 で良いのである。
ピント合わせ
ピント合わせは星景写真最大の難関と言って良いだろう。一般には遠くの景色に合わせれば被写界深度に入 るとされる。詳細は割愛するが、実のところこの方法ではシャープなピントを得ることは難しい。ピントは 最低限レンズを交換するごと、移動するごとに再度行う。シャープなピントを得る方法はいくつかあるが、 ここでは特別な道具が不要なフリンジ法を紹介する。レンズの色収差の出方を基準にした方法である。
明るい星を中心におき、ライブビューで拡大してから星が小さくになるようにピントリングを動かしてみる と星の周りに赤もしくはグリーンや青の色づきが見える。(ED やSD といった光学材料を使った高性能レン ズでは色収差も少ないので見えにくい)この色づき(フリンジ)が見えたら、小さくピントリングを左右に 回転させてみるとフリンジが消える、あるいは最小になるポイントがある。

そこが第一段階のシャープなピントのポイントだ。さらにピントリング微小に動かしながら観察すると一瞬暗い星が見えるポイントがある。そこがジャストピントの位置だ。ライブビューにもノイズがあるため、暗い星と見誤ることがあるが、カメラに振動を与えた時、動かない輝点があればそれはノイズである。難しそうに聞こえるかもしれないが慣れれば10 数秒程度で終わる作業だ。また、背面モニターしかないカメラでは、光学ルーペで拡大すると見やすくなる。虫眼鏡でも構わないので一つカメラバックに常備しておくと良い。
ピント合わせの雑学
本来ピント合わせは撮影する絞り値で行うことが正しい。実は絞り値によって最良のピント位置が変わるからだ。 星景撮影では絞り開放でピント合わせをするのはライブビューを見やすくするためだ。しかし、近年のレンズはどれも高性能になっており、絞りやズームでもピントの移動が少なく、星景写真で主に使うのは50mm以下でありピントの移動がほとんど問題にならないのだ。しかしながら、視野周辺部での収差の出方はピントの位置で微妙に違うことがある。ピント合わせに慣れてきたら、中心から少し外した位置でピントを合わせてみるのも面白い。周辺部の星の描写が微妙に変わることで写真全体が魅力的に見えることもあり、レンズ趣味の一つの遊び要素と言える。
露光の基準
ここでは星を点に写すための限界露光時間を焦点距離ごとに表にまとめた。この表は計算によって求めたものではなく多くのカメラとレンズの実写から求めた実測値である。
星は日周運動によって天空上を動き、長い露光時間では光跡として写ることは先に述べたが、この表よりも長い露光にすると星は楕円から短い線、そして長い光跡に写る。表は大判プリントなど高精細画像で点として認識できる範囲となっているため、厳しめの数値だ。ウェブなど画像サイズが小さい場合はこの表の倍程度でも十分点として認識できる。手順1-dで露光時間を5秒としているのは24mmで天の赤道付近、大雑把に言えば東もしくは西の空を撮る場合を想定している。
焦点距離の違いによる露光時間
| レンズ焦点距離 | 天の赤道付近 | 北天 | 南天 |
|---|---|---|---|
| 14mm | 8 | 10 | 8 |
| 20mm | 6 | 10 | 8 |
| 24mm | 5 | 10 | 8 |
| 28mm | 4 | 8 | 8 |
| 35mm | 3.2 | 6 | 6 |
| 50mm | 2.5 | 5 | 5 |
| 85mm | 2 | 5 | 4 |
露光時間の雑学
北天には北極星があり、天球の回転中心であるため、天の赤道付近と同じ回転角であっても移動量は小さくなるため、天の赤道付近より長い露光にすることができる。また焦点距離が短くなると許容できる時間は長くなる。しかしながら、表を見ると14mmなどではたいして長い露光時間とはなっていない。これは、画角が広いためカメラを北に向けても西か東の空も視野に入ってしまい、周辺の星の移動量が大きくなってしまうためだ。さらに広角歪みの効果も加算されている。
ISO感度と露光時間
前項では日周運動を基にした露光時間について述べたが、それを基に夜空の明るさを加味したISO感度と露光時間の組み合わせを表にした。ただし、この表は撮影手順1-dで最初の基準として設定するものであり、これで適正露光が得られるわけではない。夜空の明るさは、市街光、月明、大気状態、雲など様々な要因によって大きく変化するため、基準となる露光は在って無いようなものだ。
ともあれまずは参考程度にこの設定で試写を行い、その結果を見てISO感度を変化させることで適正露光を求めると良い。表中F値は1.4まで表示しているがF2.8を基準に考えると良い。色分けは緑がおすすめの感度と露光時間、黄色はおすすめではないがよく写る、ピンクは焦点距離および空の方向によっては星が楕円に伸びてしまう組み合わせなので、焦点距離と露光時間の図を参考に加減してほしい。グレーはおすすめではない組み合わせだ。
都市近郊の明るい夜空
| F値 | ISO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | |
| 1.4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 |
| 2.8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 |
黄色 ... おすすめではないがよく写る
ピンク ... 焦点距離および空の方向によっては星が楕円に伸びてしまう
グレー ... おすすめではない組み合わせ
山間部などの暗い夜空
| F値 | ISO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | |
| 1.4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 2.8 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | 60 | 30 | 15 | 8 | 4 |
黄色 ... おすすめではないがよく写る
ピンク ... 焦点距離および空の方向によっては星が楕円に伸びてしまう
グレー ... おすすめではない組み合わせ
ISO感度の雑学
最新のカメラではISO10万を超えるような高感度も美しい描写で夜や舞台などの写真は撮りやすくなったが、星景写真の場合高感度性能が良いとされるカメラでもISO12800より上の感度はおすすめではない。夜空、つまり星が写っていないバックグラウンドは暗いものなのでノイズが目立ちやすいからだ。
同様に本当に素晴らしい星空と言える高山の星空もノイズが目立ちやすい。むしろ少し市街光や薄雲の影響がある方がノイズが目立たず良い結果になることが多い。月明もそうだ。
そこで、月明があるときに星景写真を撮ると地上も立体的に描写されて魅力的だ。ただし満月など明るい月明かりは向いていない。半月の時に月が昇って1時間以内、月が沈む前1時間くらいの時間を狙うといい。夕日の光を浴びた風景が立体的なのと同様、斜めから差し込む月の明かりが地上の風景に力を与えてくれるのだ。
星景写真における「適正露光」とは
夜空の状態によって適正露光の設定が大きく変わることは述べたとおりだが、結果としての露光においても基準を示しにくいのが星景写真でもある。基準とすべきは星景の中の何を一番に表現するかである。星の色合いや輝きを基準にするなら星の輝度が飽和しない(白トビしない)露光、天の川や星雲の淡い光を捉えるなら低感度でたっぷりした露光、風景としての地上を大切にするなら、地上が黒ツブレしない露光。夜空全体を美しく見せるなら、バックグラウンドが中間的となる露光など、基準とする被写体によって適正な露光が変わってくるのだ。
しかしながら、まず最初の一歩としてはバックグラウンドも含めた夜空全体を考えてみるのが良い。バックグラウンドは市街光や月明を含めたものであるので、深い山奥のような暗い夜空ではなく、少し市街地を離れたような場所で撮るのが良い。そこで、ヒストグラムの山が全体の1/3前後、1/2を超えないような露光結果とすると星景写真らしい夜空と星空のバランスになりやすい。またRAWデータで撮影し、後から露光量を調整することもトライしてみてほしい。
星景写真作例
星景写真では主に50mm以下のレンズを使うことが多い。地上の風景と星を合わせて撮るため、あまり画角の狭いレンズを使う機会は少ないのだ。星座と地上の風景をバランスよく収めやすいのは24ミリ〜35ミリ。迫力ある画面を求めるなら50ミリ。2〜3個の星座とともに季節の情景を入れるなら20ミリ前後。天の川が広がる様子や前景に風景や構築物を配してダイナミックな画面を作るなら14ミリ前後といった使い分けがある。
ケンコートキナーのレンズ群の中から星景向きのレンズをピックアップし作例を紹介する。画角の違いがわかりやすいようにオリオン座付近を狙ったものを主として選んである。またいくつかの作例にはフィルターや赤道儀(スカイメモS)を使用したものがあるが、その場合はデータに記載してある。記載がないものは三脚のみを使用したものだ。フィルターやスカイメモSについては次回以降詳細を解説する予定だ。











