広角レンズ実践攻略法!写真の基本は引き算、でも広角レンズは足し算も考えよう
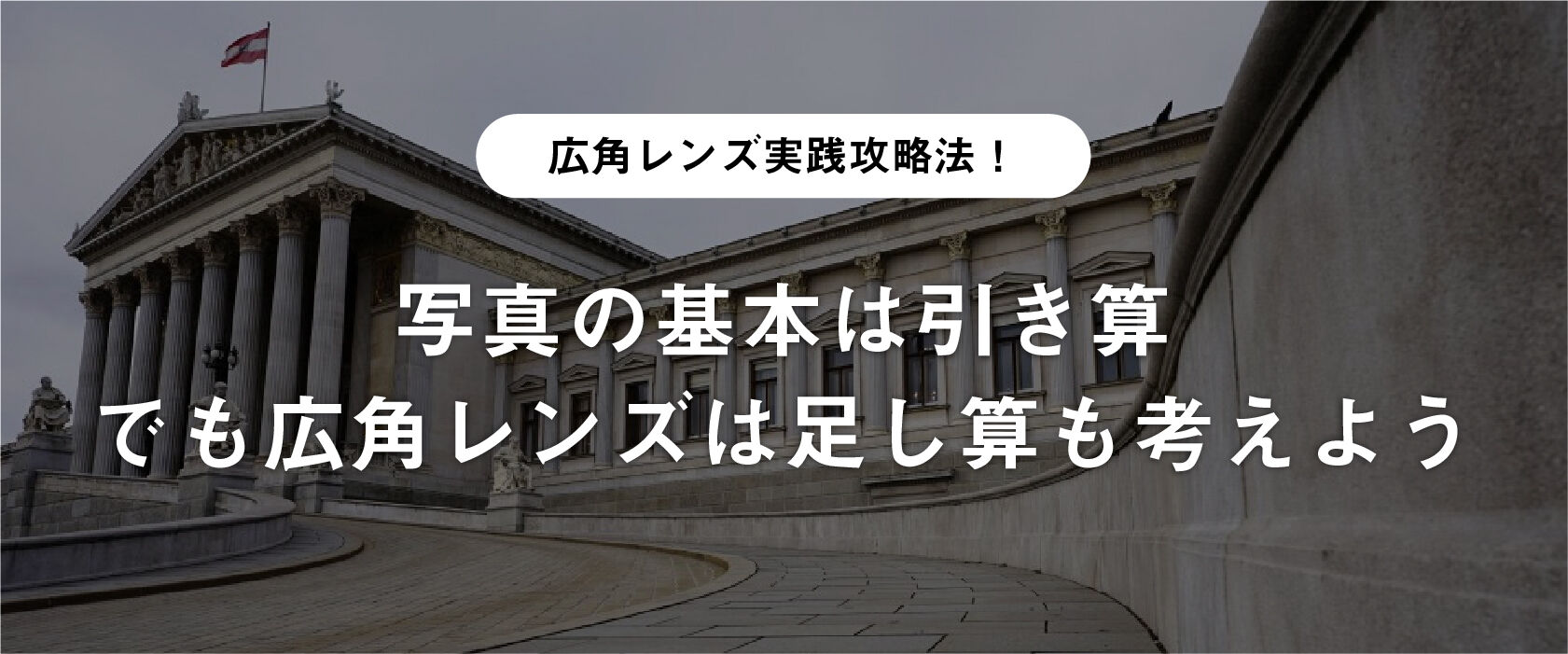
写真の基本は引き算、でも広角レンズは足し算も考えよう
写真の基本は引き算!と言われています。そのこころは「メインを際立たせるため必要のないものはなるべく画の中から排除する」ということですが、広角レンズではもう一つ「足し算」の考え方もあるということを頭に入れておいてください。
スナップ撮影のところでお話した内容と重複するのですが、メインの被写体になるものを、際立たせるために「何か別の要素を足して」メインをより際立たせるという考え方です。引き算の真逆にあるものですが「メインを際立たせる」という目的は同じです。
この写真を見てください。

少し中途半端な構図です。引き算的にはもっと建物に近寄って、画角目いっぱい建物を入れて撮影したほうがいいかな・・・と思います。いえいえ!ちょっと待ってください。ここで足し算の考え方です。撮影した場所から思い切って壁沿いに右へ移動し撮影した画がこれです。

右側に大きく壁を入れ込み導線を引きました。こうすることでよりワイド感が強調され、かつ画全体の埋まり収まりも良くなりました。広角レンズを使って撮影する場合、引き算の考え方だけではなく「足す」ことでより収まりが良くなる場合もありますので、より強調することのできるものを探して入れ込んだこと撮影するという考え方も頭に入れておいてください。
次の写真です。

引き算の考え方としては、もう一歩二歩・・・いや、もっと波打ち際まで行って、青い空、白い雲、美しい海、砂浜に置かれた黄色いボートこれで構図を作れば十分画になるじゃないか!と、思われた方、おっしゃる通りです。もちろんそうした一枚も撮影しているのですが、僕は現地の「暑さ」も画に刻みたいと思い足し算の考え方でそれを撮影することにしました。

すがすがしい一枚を撮影するのであれば「青い空」、「白い雲」、「美しい海」、「砂浜に置かれた黄色いボート」があれば十分なのですが、「暑さ」すなわち「日差し」を際立たせるための明確な「影」を足した画も撮ることにしました。一枚の中に明確な影を入れ、その影の濃さで日差しを出していく。光があるなら、影が必ず発生する。それによって涼しさを表現し光の強さも感じてもらう。何かを足していくことで体感のようなものを画に刻んでいく。これも足し算の考え方のひとつとして覚えておいてください。
色の足し算

砂浜に打ち上げられた大きな流木、その背後には夕日が落ちて空の色が美しく変わっていく。なかなかに美しいシーンです。この美しいシーンを、ググっと流木に寄ってそれをメインで撮影するというのも面白いですね。もちろん流木に寄った画も撮影しましたが、このとき僕は「色」にこだわった撮り方をする事も考えました。
夕陽の「黄金色」と暮れ始めていく空の「青」、「黄金色(黄色)」と、その反対色である「青」が一枚に同居するので、これをより強調するために何を足せばいいのかを足し算することにしました。この時、僕が選んだのは「波の反射でさらに色を出す」という選択でした。引き波のあとにのこる砂浜の反射でも色は足せるのですが、波の広がりで色を足す方がより強調することができるので、この時は強めの波が来るのを待ち、レンズギリギリまで波が押し寄せてくるところでシャッターを切りました。
広角レンズを使っての足し算の考え方としては
- 建物など物理的な要素を使いテーマを強調する
- 日差しや影など「場の空気感」を使いテーマを強調する
- マジックアワーと言われる劇的変化のある時間帯では色の足し算をしてテーマを強調する
などといった考え方があると思います。その他にも、何かを足して主題を強調するということができると思いますので、色々試していただけるとありがたいです。また、この考え方は、ほかの焦点距離でも構図構成の役に立つことがありますので、ぜひ皆さんの「テクニックの引き出し」の一つに加えておいていただけるとありがたいです。
広すぎるフレーム・・・余計なものがたくさん入ってしまう。こんな時どうすればいい?
広角レンズの画角は広いです、広いゆえに様々なものが画角に入ってきます。漫然と構えて撮影すると、色々邪魔なものがたくさん画角に入ってしまう事ってあります。実は、仕事で撮影させていただいている僕でもそういうことってあるんです。よしよし!いいのが撮れた!なんて思ってPCの大きなモニターで確認してみると「・・・あら、これはNGだな」なんてこともあります。このコラムでは、そうならないためにどういったところに気を付けているかをお話したいと思います。
まずは定番ですが、「なるべく隠す」という方法です。

ライトアップされている桜の写真です。何を隠しているのか、お分かりになりますか?
そうです、ライトアップされているという事は付近に強い点光源があります。それを入れても良いのですが、強い点光源はそれ自体が鑑賞点になってしまい桜に目が行かない場合もありますのでライトを「桜の幹」で隠しました。
次に、前ボケでいれた桜ですが、これも左上にあるライトと灯篭を隠すため前ボケとして大きめに入れ込みました。さらに、カメラ位置を少し上に持っていき反対側の土手にいる人を桜で隠し、水面に映る桜と暮れる空の青を大事にしながら構図構成し撮影しました。
何か余計なものがある場合、少し動いたり、少し高い位置もしくはしゃがみ込んで低い位置などからうまく隠せる場所を見つけたりして撮影をします。定番の手法なのですが、意外とほんの少し動いただけで上手に隠せたりすることがあります。また、ファインダーの中だけで見ていると、隠れていないことに気が付かない時があるので、じっくり撮ることができる時にはなるべく肉眼でしっかり構図を決めた後カメラのリアモニターで拡大し確認した後シャッターを切るようにしています。
あるならそれを入れて構図構成

とはいっても、それでも隠せない時ってありますよね。撮影場所によってはそっちの方が多かったりします。この写真を撮影したときもそうでした。
夕暮れの桜並木、最初頭に浮かんできたイメージは人の気配をなるべく消し、奥にある山の稜線を、画面右から大きく張り出した桜の枝の下ギリギリまで持っていき隙間をなくして撮影することをイメージしていました。しかし、いつまでたっても人が途切れないんです・・・ならば、それを入れて画にする。これはテクニックというより発想の転換ですが、撮影の現場では臨機応変も大事です。
「粘って待つも良し」ですが、発想の転換をすることでもうひとパターン違った画を撮ることもできます。広角レンズはたくさんの要素が入ってしまいます、ならば「あえて入れた画で構図を構成する」という発想の転換も必要だと思います。
ストロボを使って回りを消す
ちょっと変則的なやり方ではありますが、ストロボを焚いて暗くし回りを消すという方法を取ることがあります。

それがこの写真です
撮影データは
となっています。
シダ類の葉が森に広がっていました、ただそれだけのことなのですが非常に印象的でこれだけを撮りたいと思い撮影しました。普通に撮影すると回りの様々な緑や草などが入ってしまうため、この時はストロボを使い一点だけ明るくして回りを暗くすることにしました。
この画のテーマは「葉の広がりとその姿」です、フィッシュアイレンズで思い切り近寄り、葉の広がりを強調するため放射線状になるよう配置、その後先ほどの撮影データの設定で撮影しました。ISO200にしたのはストロボの明かりとの明暗差をより強くするために低い感度を選んでいます。ストロボの光は±0のまま、絞りはあまり極端に絞るとコントラストが付きすぎてしまい葉部分の明暗のグラデーションが失われてしまうため中間絞りのF5.6を選択しました。

では、暗がりの部分をレタッチソフトで明るくしてみました。如何でしょうか?やはり周りは雑多な感じですね、これを構図の工夫で隠すのはちょっと大変ですし、あるもので構図構成というのもなかなか難しい。ということで、この時僕はストロボを使うという事を選択しました。その他にも様々な手法があるとは思うのですが、このように「もう一手何か使う」ことで解決していくこともできます。
それでも余計なものが入ってきてしまう場合は、最終的にレタッチソフトに頼るという選択もあります。その場合は、撮影時レタッチでの作業が楽になるように、消しやすい場所に余計なものを配置するなどの工夫が必要になります。しかし、その前に考えていただきたいことがあります。それは、「頭に浮かんだイメージ」を具現化するにあたって本当にその焦点距離で正解なのか?という事です。
ここまで、「構図を工夫する」、「発想の転換で敢えて入れて構図構成する」、「何かほかの道具を使って隠す」、「レタッチソフトで隠す」といった方法をお話しました。それでも隠しきれない場合は、もしかするとイメージと焦点距離が合っていない場合があります。そうした焦点距離の特性も考えながら、一度別のレンズに変えてみた上で構図を構成してみてください。
オススメの広角レンズ


FíRIN 20mm F2 FE AF
製品情報
FíRIN 20mm F2 FE MF
製品情報
atx-i 11-20mm F2.8 CF
製品情報
opera 16-28mm F2.8 FF
製品情報
atx-i 11-16mm F2.8 CF
製品情報
AT-X 14-20 F2 PRO DX
製品情報

この記事の作者

小河 俊哉(おがわ としや)
東京都出身。
自動車整備士、カースタントマンなどを経てフリーフォトグラファーとなる。
自然、風景、クルマ写真などを専門とし雑誌、クラッシックカーイベントなどで活躍。 現在、作品集作成のため精力的に国内外で撮影中。








